今や世界のあらゆる場所で紛争が勃発し、新型兵器は補充され続け、いつの日か近い未来、第三次世界大戦へと広がってゆくのではと誰もが心底不安を抱えている時代。そんな今だからこそ、映画を通して戦争の矛盾と人間の愚かさを直視し続けたアラン・レネによるドキュメンタリー『夜と霧』(1956年)と『ヒロシマ・モナムール(邦題は『二十四時間の情事』で公開された)』(1959年)を続けて鑑賞することにした。
『ヒロシマ・モナムール』はアラン・レネの長編監督デビュー作であり、かたや短編ドキュメンタリー作品『夜と霧』は、アウシュヴィッツのユダヤ人強制収容所でユダヤ人が虐殺したホロコーストを告発した重く濃密な作品である。たった4年の間に、ホロコーストとヒロシマという歴史的大罪二つをテーマでここまで「問題を正視した目線」で作品が作れるのはすごい。『ヒロシマ・モナムール』は、男女のロマンチックなアヴァンチュールの体裁にはなっているが、漫画『はだしのゲン』を実写化したような原爆直後の再現ドラマが挿入されたり、被爆者たちの実際の映像が使用されたりと、そこにある覚悟はかなり本気。「水素爆弾は原子爆弾1500発の規模があるとしたら、現在製造されている4万個の爆弾にはどれぐらいの力がありますか? 悲しいことに、人間の政治的知性は科学的知性と比べて一千倍以下に劣っている。水爆テストをやめろ!NO MORE HIROSHIMA!」と無言のまま看板だけを持った群衆が練り歩くシーンをしっかりと差し込んでゆく。根底には力強い反戦のメッセージがある。映画の撮影で広島に来たフランス女優と日本人建築家(自称。働いているシーンはない)とのアヴァンチュールは美しいが、彼らは根底に隠された恐ろしい物語を伝えるための語り部でしかない。または、この二人の関係は強烈な何かのメタファーとしてだけ準備されたようにも感じる。彼女が「喫茶どーむ」かどこかで男性に過去を語りながら涙をこぼすシーン。「死んでゆく彼の体と、自分の体に、ほんの少しの違いも感じられなかったわ。時には、人生がもたらす問題について、考えることをやめなくてはいけない。そうしなければ、窒息してしまう」と言う彼女は、自身の過去について語っているのだが、それは同時にヒロシマと、それにまつわる物語への、アラン・レネ自身のメッセージでもあるのだろう。

そしてもう一本は、ユダヤ人強制収容所で起きたことを、記録映像を交えて圧倒的なリアリズムでドキュメントした短編作品『夜と霧』。この作品は、全世界の人が必ず一度は見るべき最重要作品である。上映当時は、世界に衝撃を与え論争が巻き起こったという。過激なシーンが数分のカットされてやっと日本でも上映された。美しい田園風景からこの映画は始まる。「農道も、恋人があるその道も、行楽地で賑わう市場の道も、その先には強制収容所がありました。」そしてカメラは鉄条網で覆われた広大な収容所を映し出す。「収容所には、山小屋風、日本風など、さまざまなスタイルがありました」と観光ガイドのようなイントロから始まり、カメラは少しづつ内部へと迫ってゆく。逃げるなど敵わない、広大で計画された、悪意の中へ。
「どこかの街で人生を謳歌していた人たちのために、彼らが人生を終える場所がここでは着々と用意されていたのです」という内容のナレーションに、背筋がゾッとする。そういう視点で考えたことはなかったが、確かにそうなのだ。緻密に計算され組織化されたやり方で日常から引き剥がされた彼らは、この空間に閉じ込められ、命が奪われていった。その数何百万人。一人一人の描写が生々しく、暮らした人たちの姿がありありと浮かんでくるほど、その数に吐き気を覚える。「この場所は将校たちの部屋です。彼らに気に入られた女性たちは、この場所で夜の相手をすることで、ほんの少しだけ命を繋ぐことができました。結末は同じでしたが」と建物の中で生きてきた人たちの「物語」を説明する。「時には、その部屋の窓の下がほんの少し開かれ、隠れて待つ仲間のためにパンが落とされたこともあるでしょう」と。精一杯生きようとする彼らの姿が目に浮かぶほど、切なく悲しい。
ロベルト・ベニーニ監督の映画『ライフ・イズ・ビューティフル』の後半部分、モヤの向こうに一瞬だけ「死体の山」が映し出されるが、はじめて観た時「なんだこれは?!そんなわけないだろ」と信じられなかった。しかし実際にはそうではなかった。そんなものではなかったのだ。あそこで見た光景なんて、わかりやすいように作られた「小さな山」でしかなく、本当は、何十倍もの死体の山が広がっていたのだ。この映画『夜と霧』には、それが正しく記録されている。ホラーSFで、惑星一つが死体で覆われているような世界、わかりやすいところでは漫画『ベルセルク』でベヘリットの力で開かれた異界「蝕」の風景。切り取られた髪の毛だけを集められた空間は、想像をはるかに超え、果てしなく広がる。挙げ句の果てに「この髪の毛で絨毯を作りました」とか、「皮膚から紙を、肉体からは石鹸を作りました」という説明と映像に、恐怖と嫌悪感はマックスに。早くこの空間から逃げ出したい、と心から思えてくる。
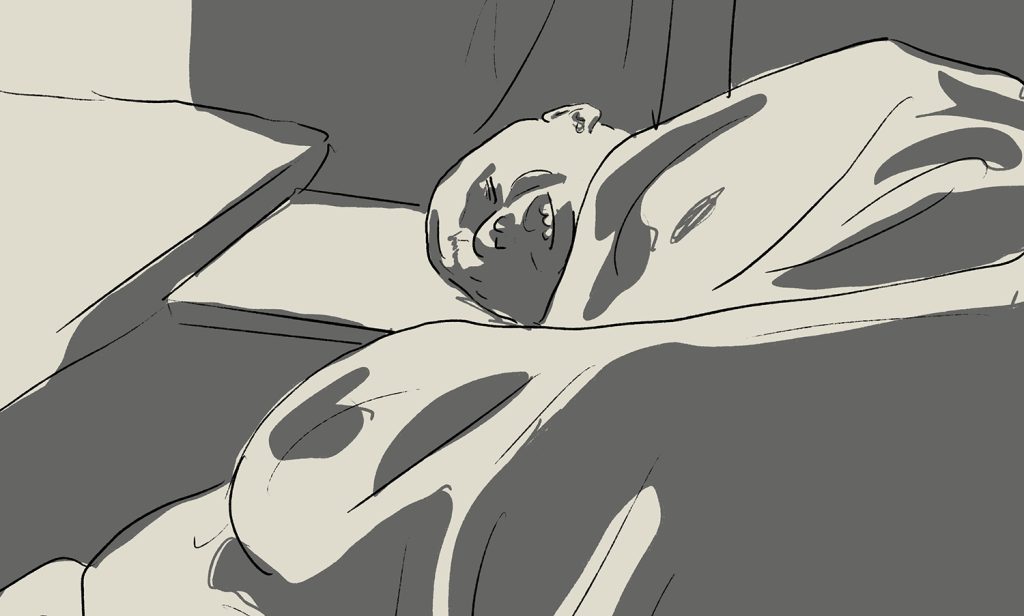
この『夜と霧』という名前の由来は、ナチスドイツに抵抗したものは「夜と霧」の中で消えるように連れ去るべし、とヒトラーの部下ヴィルヘルム・カイテル総長が発した指令のことだという。もともとはヒトラーが好きだったヒャルト・ワーグナーの作品「ニーベルハイム」の中に「Nacht und Nebel, niemand gleich!(「夜と霧になれ、誰の目にも映らないように!」)」という言葉が出てきたので、そこから命名したらしい。ん?なんだこの卑怯な言葉は? 誰の目にも映らないように夜と霧になることなんて、許されるはずはない。そんな卑怯な思想で、人々を誘拐し、殺してきたとは。許されるはずはない。『ヒロシマ・モナムール』の最後に主人公の女性は「あなたが歌になってしまう」と、忘却が全ての飲み込んでいくことへの恐怖を語り始める。そんなことは決して許されない。ヒロシマもアウシュビッツも、決して忘却されはいけないのだ。
だけど大丈夫だ。『夜と霧』と『ヒロシマ・モナムール」があるのだから。マルグリット・デュラスが執筆した美しい物語と共に語られるヒロシマ、そしてアウシュビッツの恐ろしさを真っ直ぐに見つめるドキュメンタリー。アラン・レネが残してくれた二つの作品には、時を超えて訴え続ける力があるのだから。これから何度も愚かな人間たちは恐ろしいことを考え、悪意に身を任せてゆくことだろう。「政治的知性は科学的知性と比べて劣っている」とアラン・レネが言っているように、愚かな人間たちが世界を動かしてしまうのだ。だからこそ過去の過ちは繰り返してはいけない。そんなの糞食らえだ。言ってみれば、「夜と霧になるな、誰の目にも映る光になれ!」だ。
